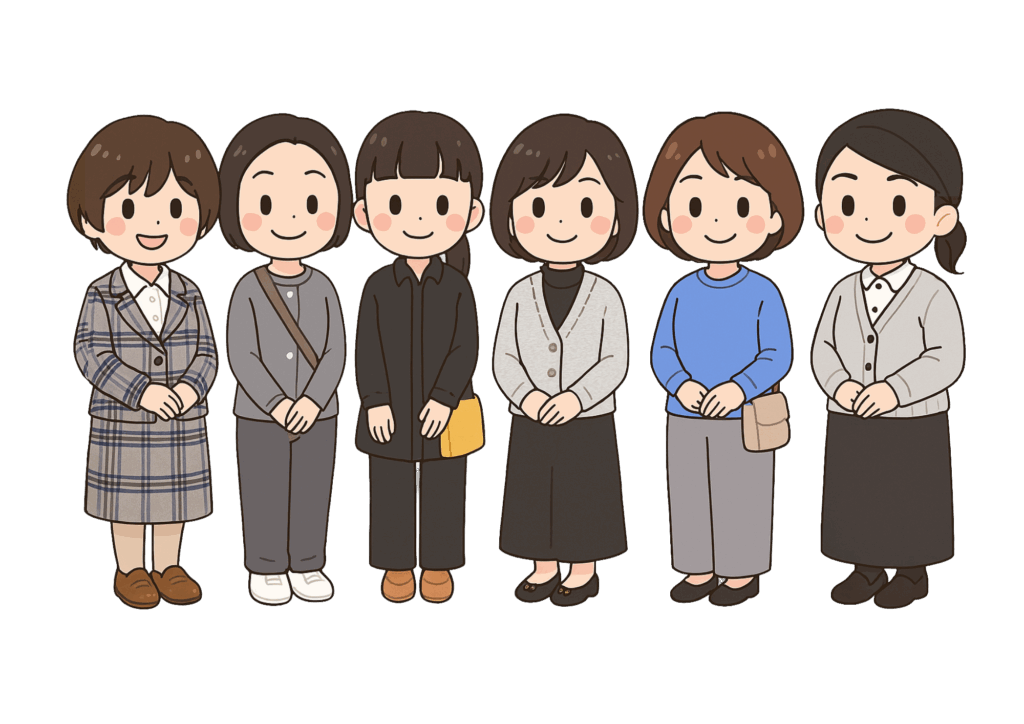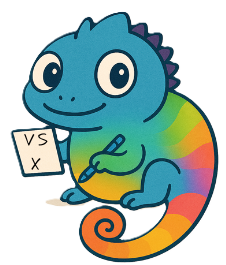2024年度4月より会長を拝命いたしました。本会の活動の場であった東京大学アウトステーションのビームラインがSPring-8から移設され、4月9日より待望の次世代高輝度光源NanoTerasuでの運用が開始されました。これを機会として本会の活動の場を特定の施設やビームラインに限らずに、VUV・SX波長域の光を使ったサイエンス全体を対象にすることを目指して、本VSX懇談会のミッション再定義が議論されました。2024年1月の日本放射光学会年会の総会にて趣旨が同意され、同3月にVSX懇談会会則が改定されました。こうした背景の中、会長に就任いたしましたが、これからの時代はVUV・SX光源で高い国際競争力をもつ放射光ビームラインに留まらず、自由電子レーザーや高次高調波レーザー光源を利用する研究者など、これまでの懇談会の活動範囲を積極的に拡張し、光源の種に囚われずにVUV・SX光の利活用を活発に議論していくフェーズであると感じています。各要素技術が成熟しつつあり、本懇談会が中心となって異分野交流を強化することで、世界に先駆けて新たな一歩を踏み出す時です。
複雑系・不均一系をはじめとして、機能や物性発現のメカニズム解明が切望されている多彩な物質群があり、特にこれまで先端光源に馴染みが薄かったコミュニティを中心として多くの研究ニーズが待ち構えています。人類はVUV・SX光のコヒーレンス特性をまだまだ利用できていません。高いキュリオシティに基づいたニーズプルの牽引力と、高い光源技術と開発力によるシーズプッシュの両輪を我が国の強みとし、一丸となって世界を先導する新たなサイエンスの創発を目指しましょう。そのためには放射光コミュニティの裾野の拡大を図りつつも、レーザーコミュニティとの協働を含めた抜本的な意識改革と、それに付随した組織体制による横串としての支援が欠かせず、本VSX懇談会の重要な役割と捉えております。今後、ワーキングや研究会などを通して、本会の新しい姿を皆様と議論し具現化していきたいと思います。今後とも皆様の活躍とVUV・SXサイエンスへのご貢献を期待しております。
VUV・SX高輝度光源利用者懇談会
日本国内には10余りの放射光施設が存在し、その全てがVUV・SX(真空紫外・軟X線)領域をカバーするビームラインを有しています。これらの施設は、特色ある最先端の計測技術を提供し、基礎から応用まで幅広い分野の研究を力強く支えてきました。また、VUV・SXコミュニティーは、国内施設の利用促進に留まらず、海外施設の利用動向の共有や国際的なユーザー受け入れを積極的に推進することで、最先端技術の共有と現場の研究開発(R&D)への還元を図り、コミュニティー全体の研究力向上に向けた文化を長きにわたり育んでまいりました。今後は、放射光、自由電子レーザー、高次高調波レーザーなど、光源の種類に関わらず、VUV・SX光の利活用や今後の展望について議論し、利用者間の連携を深め、持続的な光科学の発展に寄与することを目的としています。
私たちVUV・SX高輝度光源利用者懇談会は、国内外の施設・研究機関の「横のつながり」を最も大切にし、研究会やニュース発行などの継続的な活動を通じて、VUV・SX領域における研究交流と次世代の人材育成に貢献しています。
会長挨拶
VUV・SX高輝度光源利用者懇談会設立の経緯
VUV・SX高輝度光源利用者懇談会は、1995年に設立されました。当時、軟X線(SX)および真空紫外線(VUV)の高輝度光源計画が東京大学物性研究所軌道放射物性研究施設を中心に進められ、同施設の教職員が主体となって東京大学としての光源施設の設立を推進していました。この計画の実現支援、計画後の放射光利用の推進、さらには利用者間の協力体制の構築を目的として、懇談会が発足しました。発足当初は、軌道放射物性研究施設における放射光利用科学の方向性の策定、建設協力体制および共同利用体制の確立を主要課題としており、光源計画の動向や技術情報、利用研究に関する情報共有を通じて、これらの目的達成を目指していました。
その後、2005年に、高輝度光源計画は中止が決定されましたが、懇談会の活動はSPring-8における東京大学ビームラインの建設支援および利用推進へと発展的に移行し、利用者間の情報交換や実験技術の向上に向けた議論を継続しました。また、SPring-8に設置された東京大学ビームラインの維持・管理・発展を軌道放射物性研究施設が担い、懇談会はその利用促進および利用者間の協力体制の強化に寄与してきました。
さらに近年では、自由電子レーザー(FEL)や高次高調波レーザー(HHG)といった次世代光源の利用、NanoTerasuno施設での研究推進、共用実験の支援など、活動の対象をより広範な高輝度光源研究へと拡大しています。 設立以来、懇談会は参加者間の技術的議論や利用経験の共有を通じて、国内のVUV・SX領域の光源の利用研究の基盤強化、利用環境の向上、そして研究者・技術者間の協力体制の構築に継続的に貢献してきました。東京大学物性研究所軌道放射物性研究施設が中心となり、同施設が一貫して主体的に関与してきたことにより、設立当初から現在に至るまで、研究者コミュニティの結束と光源利用技術の発展を支える重要な役割を果たしています。
会則
VUV・SX高輝度光源利用者懇談会
![]() VUV・SX高輝度光源利用者懇談会会則20240311.pdf (0.5MB)
VUV・SX高輝度光源利用者懇談会会則20240311.pdf (0.5MB)
2024年改訂
![]() VUV・SX高輝度光源利用者懇談会会則20240918.pdf (0.53MB)
VUV・SX高輝度光源利用者懇談会会則20240918.pdf (0.53MB)